パーソナルトレーナーや小規模ジムのオーナーとして事業を営む場合、万一の事故やトラブルに備えて適切な保険に加入することが極めて重要です。
近年、トレーニング指導中のケガや健康被害の報告が相次いでおり、消費者庁も実態調査に乗り出すほどです。
本記事では、パーソナルジムの責任者経験があり、企業の福利厚生などにトレーナーを派遣している当社代表の笹森が、パーソナルトレーナー・ジムオーナーが保険に入るべき理由を解説。
また、主要な保険種類の補償内容、実際に加入できる保険商品の比較、そして現実に起こった事故・賠償事例についても網羅的に解説します。
保険加入の手続きや必要書類、契約時のポイントも取り上げますので、リスク管理に不安を感じるトレーナー・経営者の方はぜひ参考にしてください。
パーソナルトレーナーの
検索&マッチングサイトへ登録しよう!
目次
パーソナルトレーナーやジム経営者に保険が必要な理由

パーソナルトレーナー事業にはさまざまなリスクが存在するため、適切な保険で備えることが不可欠です。
ここでは、特に注意すべきリスクを事故・賠償、器具損壊、所得補償などの観点から説明します。
1.顧客のケガ・賠償リスク
マンツーマンのトレーニング指導中に顧客が負傷するリスクは常に付きまといます。
どんなに注意していても、重いダンベルやバーベルを扱う場面ではヒヤリとすることがあるでしょう。
もし顧客がトレーニング中にケガをすれば、治療費や慰謝料など法的賠償責任を問われる可能性があります。
フリーランスのトレーナーであれば、それらはすべて自己責任で負わねばなりません(ジムに雇用されているトレーナーなら通常ジム側が責任を負います)。
また、トレーナーの指導ミスによる体調悪化や、提供したサプリメントが原因の健康被害など、様々なケースで損害賠償リスクが発生し得ます。
2.器具・設備の損壊リスク
トレーニング設備や器具の管理不備もリスク要因です。例えば「マシンの不具合で顧客が転倒した」「トレーニング中に器具が倒れて他人の持ち物を壊してしまった」といった場合、施設や器具が原因の事故として賠償責任を問われます。
さらに、ジムの建物やマシンなどの設備そのものが火災・台風・地震などの災害や事故で損傷するリスクも考慮すべきです。設備の修理・買い替えには高額な費用がかかるため、これら施設・器具の損害に備える保険も重要になります。
3.トレーナー自身の傷病・所得リスク
パーソナルトレーナー自身がケガをしたり病気になった場合のリスク管理も見落とせません。
自営業のトレーナーには会社員のような健康保険の「傷病手当金」(病気やケガで働けない場合の収入補償制度)が無いため、働けない期間の収入減は直接生活に影響します。
例えばトレーナーがトレーニング中に負傷して長期間働けなくなった場合、治療費負担だけでなくその間の収入喪失という打撃を受けます。所得補償保険に加入しておけば、自身の傷病で仕事を休まざるを得ない期間の収入減を補填することが可能です。
4.自然災害・休業リスク
頻度は高くないものの、火災や爆発、台風・地震などの災害リスクにも備えておく必要があります。小規模ジムであっても、火災により施設が焼失したり台風で建物が破損したりすれば、営業休止を余儀なくされ多大な損害を被ります。
こうした場合に休業補償保険(営業できない期間の売上損失を補填する保険)に入っていれば、家賃や人件費など固定費の支出をカバーできます。滅多に起こらないからと対策を怠ると、万一の際に事業継続が困難になる恐れがあるのです。
以上のように、パーソナルトレーナーやジム経営者は顧客への賠償リスク、設備の損壊リスク、自身の傷病による収入リスク、そして災害リスクを抱えています。
実際にフィットネス業界では、設備故障・自然災害・トレーニング中のトラブルなどに直面し、「もし保険に入っていなかったら…」と背筋が凍る思いをした事例もあります。こうした想定外のトラブルから事業と生活を守るために、保険加入は欠かせない備えなのです。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
パーソナルトレーナー向け主要な保険種類と補償内容

上記のリスクに対応するため、パーソナルトレーナーやジムオーナーが検討すべき主要な保険の種類を整理します。傷害保険・賠償責任保険・所得補償保険・器具損害保険の各保険について、その特徴や補償範囲を解説します。
1. 傷害保険(トレーナー自身のケガに備える保険)
傷害保険とは、契約者本人が事故によりケガを負った場合に保険金が支払われる保険です。パーソナルトレーナーは日頃から体を酷使しますし、移動中の交通事故やトレーニング指導中のアクシデントで自分自身が負傷する可能性もゼロではありません。
傷害保険に加入しておくと、例えば骨折・捻挫などで入院・手術となった場合に所定の給付金を受け取れます。また不慮の事故による後遺障害や死亡時にも保険金が支払われ、遺族の生活保障にもなります。公的医療保険では賄えない部分も含め、自身の治療費や休業中の生活費に充てられる資金を確保できる点で心強い保険です。
パーソナルトレーナー向けの団体保険では、後述の資格団体NESTAでオプションとして傷害保険に加入できるコース(月額2,000円)が用意されている例があります。これはトレーナー自身がトレーニング中などに負傷した際の補償を手厚くするものです。
傷害保険単独の商品も多数の損保会社から提供されており、補償内容(入院日額、手術給付金、後遺障害保険金など)や保険料を比較して選ぶことができます。自営業者にとって自身の体が資本である以上、万一の怪我に備える傷害保険は「自分自身への保険」と言えるでしょう。
2. 賠償責任保険(指導中の事故による損害賠償に備える保険)
賠償責任保険(損害賠償保険)は、トレーナーの業務中のミスや過失によって顧客や第三者にケガを負わせたり物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金や訴訟費用などを補償する保険です。
パーソナル指導中の事故でトレーナーが法的責任を問われる事例は年々増えており、一部のフィットネスクラブではトレーナーに保険加入を義務付けるケースもあるほど重要視されています。
賠償責任保険で補償される主な費用には、被害者への治療費・慰謝料等の損害賠償金、示談交渉や裁判になった場合の弁護士費用・裁判費用(争訟費用)、事故直後の応急手当費用や二次被害防止の費用(緊急措置費用)などがあります。
具体的なケースとしては、「トレーニング中に補助が不十分で顧客を転倒させ負傷させてしまった」「マシンの管理ミスで器具が倒れ、施設の鏡を割ってしまった」などで生じる賠償責任が挙げられます。対人事故だけでなく対物事故(他人の所有物を壊した場合)も補償対象です。
ちなみに、賠償責任保険にはいくつか種類があります。トレーナー個人が加入する個人賠償責任保険では、業務中の事故による対人・対物賠償を幅広くカバーできます。また自分が管理・運営するジム施設が原因で起こった事故に備える施設賠償責任保険もあります。
例えば「床が滑りやすく顧客が転倒した」「ジム設備の欠陥でケガをした」といった施設側の不備による事故に対応する保険です。パーソナルジムを構えるオーナーであれば、個人賠償だけでなく施設賠償責任保険にも加入しておくことで、施設管理者としての賠償リスクにも万全を期すことができます。
補償額については、近年の賠償請求高騰も踏まえ1事故あたり1億円程度を上限とするプランが主流です。
後述する資格団体の保険でも対人1億円まで補償といった契約が多く、安心感があります。なお、賠償責任保険の適用範囲や上限額、免責金額(自己負担額)は商品によって異なるため、補償範囲を十分に確認し、できるだけ幅広いリスクに対応できるものを選ぶことが重要です。
3. 所得補償保険(働けない期間の収入減に備える保険)
所得補償保険とは、病気やケガで働けなくなった場合の収入減を補償する保険です。自営業のパーソナルトレーナーが長期間仕事を休まざるを得なくなった場合、公的保障が乏しいため収入が途絶え生活が立ち行かなくなる恐れがあります。そうした事態に備え、所定の就業不能期間について毎月一定額の給付金を受け取れるのが所得補償保険です。
例えば「重い病気にかかり数ヶ月間トレーニング指導ができない」「怪我で入院・リハビリのため当面仕事を休む」といったケースで、所得補償保険に加入していれば就業不能期間中の所得の一部(もしくは全部)を保険金でカバーできます。給付額や支払期間は契約内容によりますが、日額もしくは月額で定められ、一定の免責期間(例:連続○日以上働けない場合に支払い開始)が設けられるのが一般的です。
資格団体JATI(日本トレーニング指導者協会)では、会員向けサービスとしてトレーナー自身のケガ・病気で収入が減った場合に補償する所得補償保険を提供しています。年齢により保険料は異なりますが、こちらに加入すれば健康保険や労災の有無に関係なく所定の給付金が受け取れるため、フリーランスでも安心感が得られます。特に家族の生活を支える立場であれば、自分に万一のことがあっても収入源を確保できる所得補償保険への加入を強く検討すべきでしょう。
4. 器具損害保険・財産保険(設備や備品の損害に備える保険)
器具損害保険とは、ジムのマシンやトレーニング器具など事業用の設備・備品が損壊した場合の修理費・再調達費を補償する保険です。一般的には単独の「器具保険」というより、火災保険に動産総合保険(店舗財産保険)を付帯する形で設備・什器への損害もカバーするケースが多いでしょう。
補償される典型的なリスクは、火災・落雷・爆発や風災(水害)・地震といった自然災害による施設・設備の損壊です。例えば「落雷でジムのマシンの電子部品が故障した」「台風で屋根が飛ばされ雨水で器具が水浸しになった」といった被害がこれに該当します。こうした災害時に保険に入っていれば、設備の修理代・買替費用が保険金でまかなわれます。実際、あるジムでは台風の強風で店舗シャッターが破損しましたが、火災保険(風災特約)に加入していたおかげで数十万円の修理費が保険金で支払われ、営業停止も最小限で済んだという例があります。
また、盗難や破損事故による器具の損害も対象となる契約があります。高額なトレーニング機器が盗まれたり、誤って器具を落として壊してしまった場合など、動産総合保険でカバーできる場合があります。契約内容によって補償範囲が異なるため、自ジムの設備リストとリスクを洗い出し、必要に応じて特約を付けることが重要です。
なお、小規模ジムの場合、建物を賃貸しているケースが多いと思われます。その場合でも、内装や備品はテナント側の財産として保険付保できますし、借用施設そのものに損害を与えた場合の補償(借家人賠償責任など)も含めて契約することが可能です。
例えばスポーツ安全保険では、借りた体育館の壁を壊した場合に保険金が出ますが、自身が所有・管理する器具の損壊は対象外とされています。自前の設備を守るには、それ専用の補償を確保する必要がある点に留意しましょう。
その他のオプション補償
上記4種の保険以外にも、事業形態によっては検討すべき補償があります。例えば、トレーナーが顧客の個人情報(健康状態や連絡先等)を扱う場合、万一情報漏洩事故が起きた際の個人情報漏洩保険が役立ちます。
また、法人経営のジムで従業員を雇っているなら労災保険(労働保険)への加入が義務ですし、フリーランスであればフリーランス協会の賠償保険に加入する選択肢もあります。事業内容や規模に応じて必要な補償を過不足なく組み合わせることが大切です。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
パーソナルトレーナー・ジム向け保険商品の比較

では、実際にパーソナルトレーナーや小規模ジムオーナーが加入可能な主要保険商品にはどのようなものがあるでしょうか。
代表的な資格認定団体の保険および関連する保険サービスをいくつかピックアップし、保険料や補償内容、特徴を比較表にまとめました。
| 保険サービス・提供団体 | 年会費・加入条件 (※必要資格) | 保険料(年間) | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|
| NESTA(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会) 賠償責任保険 | 年会費 12,000円 (NESTA-PFT資格保有者) | 0円(会員特典で保険料無料) | 資格認定団体の会員特典で賠償責任保険に自動加入。追加費用なしで補償が付帯。 ※傷害保険オプションあり(月額2,000円)で自身のケガにも備え可。 |
| NSCAジャパン(日本ストレングス&コンディショニング協会) 賠償責任保険 | 年会費 12,960円 (NSCA-CPTなど資格保有者) | 9,600円/年 | NSCA認定資格保有者向け。会員年会費に加え保険料が必要(年間9,600円)。補償額詳細は要問い合わせだが、他団体と同水準の高額補償と推定される。 |
| JATI(日本トレーニング指導者協会) 賠償責任保険 + 所得補償保険 | 年会費 10,000円 (JATI-ATI資格など不要※会員なら加入可) | 8,400円/年 (月額700円) | トレーナー向け団体保険サービス。賠償責任と所得補償の両方に加入可能。会員なら資格の有無に関わらず利用可。保険料は年齢条件で変動(所得補償)。 |
| JHCA(日本ホリスティックコンディショニング協会) 賠償責任保険 | 年会費 10,500円 | 3,800円/年 | ホリスティックコンディショニング関連の資格団体。保険料が比較的割安(年3,800円)で対人1億円の補償が受けられるのが特徴。年度途中加入時は月割計算。 |
| 日本スポーツ協会(JSPO)公認指導者向け保険 賠償責任 + 傷害保険 | ※JSPO公認スポーツ指導者資格 | Aプラン: 23,030円/年 Bプラン: 13,980円/年 | スポーツ庁管轄の公的団体による指導者向け総合保険。保険料に賠償責任と傷害補償がセット。資格区分によりプラン選択。年度途中加入は月割計算。 |
上記以外にも、フリーランス協会の一般会員(年会費1万円程度)になると職種問わず個人賠償責任保険(国内無制限※示談代行付き)が自動付帯される制度もあり、パーソナルトレーナーも利用可能ですが、所得補償や器物損壊補償は含まれないため、専門団体の保険と比べて補償範囲は限定的です。
自分の活動内容に合った補償が揃っているか、上記のような各プランの補償内容・費用・加入条件を比較検討することが重要でしょう。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
パーソナルトレーナーの指導中の事故・賠償トラブルの事例

実際にパーソナルトレーニング中に発生した事故や、それに伴う賠償トラブルの事例をいくつか紹介します。近年は「パーソナルトレーニングによる健康被害」が社会問題としてクローズアップされつつあり、消費者庁にも被害相談や報告が寄せられています。
こうした事例を知ることで、どんなリスクに備えるべきか具体的にイメージできるでしょう。
ケース1:過度なトレーニング指導により顧客が負傷 – 損害賠償請求
あるスポーツクラブで、パーソナルトレーナーが減量目的の顧客に対し過度なトレーニングを継続的に課した結果、顧客が腰椎椎間板ヘルニアを発症し**「腰の骨を折る」重傷を負った事例があります。30代女性だった顧客は、前かがみの姿勢でバーベルを持ち上げる運動を2ヶ月にわたり続けさせられた結果、腰椎の骨折に至ったとのことです。このケースではトレーナー(および雇用するスポーツクラブ)に対し損害賠償請求の裁判**が起こされています。過度な負荷指導や極端な食事制限などにより利用者に健康被害が生じた場合、指導者側の過失が問われ高額な賠償責任を負う可能性があります。
実際、国民生活センターのまとめによると2017年~2022年の約5年間で、パーソナルトレーニングに関するケガや事故の相談が105件も寄せられており、その4人に1人は治療に1ヶ月以上要する重い被害でした。こうした現状を受け、消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)は2023年5月、「パーソナルトレーニングによる事故・健康被害」の原因調査に乗り出しています。トレーナーとしては、顧客の体調や限界を見極め適切な範囲で指導することはもちろん、万一の賠償リスクにも備えておかなければなりません。
ケース2:施設の欠陥・ミスが原因で事故発生 – 施設賠償責任
スポーツジムの施設や設備に起因する事故も報告されています。例えば「ジムの床が滑りやすく整備不良だったために利用者が転倒し骨折した」「備え付けマシンのボルト緩みを放置した結果、使用中にパーツが外れてケガをさせてしまった」等のケースです。ある事例では、フリーウェイトエリアの鏡が割れていたのに適切に交換されず、トレーニング中の利用者が破片で負傷する事故も起きています。これらは施設管理上の過失として施設賠償責任保険の対象となり得る事故です。
また、韓国で2017年に発生したスポーツクラブ火災事故では9階建てビルのジムが火元となり多数の死傷者を出しました。このように施設そのものの災害や欠陥による重大事故も起こり得ます。日本の小規模ジムでも、たとえば空調機器のショートによる火災やガス漏れ爆発などが万一起これば、利用者への補償のみならず近隣への損害賠償も発生しかねません。施設賠償責任保険や火災保険で幅広く備えておくことが、経営者としてのリスクマネジメントとなります。
ケース3:その他のトラブル事例
- 物損事故と弁償: パーソナルトレーニング中にトレーナーが誤って顧客の私物を破損してしまう事例もあります。JATIの資料では「クライアントが転びそうになり支えた際、誤ってその方の高級腕時計を壊してしまった」というケースが紹介されています。この場合、対物賠償として修理費や新品購入費を弁償する責任が生じますが、賠償責任保険に入っていれば保険金でカバー可能です。
- プロテイン提供による体調不良: ジムでトレーナーが販売・提供したプロテインやサプリメントが原因で顧客が食中毒やアレルギー症状を起こした場合、**生産物賠償責任(PL保険)**の問題となります。「サービスの一環で出されたプロテインドリンクで腹痛を起こした」等の相談も実際に報告されており、この場合も損害賠償の請求対象となり得ます。施設賠償保険にPL特約を付けるなどして備えることが望ましいでしょう。
- トレーナー自身の事故: トレーナーが移動中に交通事故に遭い入院したケースや、デモンストレーション中に自ら負傷してしまったケースもあります。これにより予約セッションを長期間キャンセルせざるを得ず、顧客とのトラブル(返金交渉)や収入減少に見舞われることがあります。傷害保険や所得補償保険で自らの治療費・生活費を確保するとともに、必要に応じ代替トレーナーを立てる契約上の取り決めをしておくなどリスク軽減策が考えられます。
以上の事例から明らかなように、パーソナルトレーナー・ジム運営には思わぬ形で事故・トラブルが発生し得ます。「自分だけは大丈夫」と油断せず、起こりうる最悪のケースに備えて保険を手配しておくことがプロフェッショナルとしての責任と言えるでしょう。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
保険加入の流れと実務ポイント

最後に、実際に保険へ加入する際の手続きの流れや必要書類、契約時の注意点など実務的なポイントを解説します。いざ保険を契約しようとした際に戸惑わないよう、事前にステップを把握しておきましょう。
1. 加入方法の選択 – 代理店経由か団体特典か
パーソナルトレーナーが保険に加入する方法としては大きく3つのルートがあります。
- 保険会社に直接相談して契約する: 補償内容が明確に決まっている場合は、損害保険会社の窓口や公式ウェブサイトから直接申し込むことができます。最近はオンラインで見積もり・契約まで完結できる商品もあります。不明点があれば遠慮なく問い合わせ、納得して契約しましょう。
- 保険代理店を通じて契約する: 保険のプロである代理店に相談すると、複数社のプランを比較しながら最適な保険を提案してもらえます。トレーナー業界に詳しい代理店担当者であれば、業種特有のリスクに合った商品を教えてくれるでしょう。忙しい中で自分で各社を調べるのが難しい場合、代理店をパートナーにするのも有効です。
- 資格団体の会員特典として加入する: 前述したように、NESTAやJATI等の資格認定団体では会員向けに保険制度を用意しています。すでに資格を保有している場合はその団体の保険に加入するのが手軽ですし、これから資格取得を検討している場合も「保険加入目的」で団体を選ぶ一つの要素になります。団体保険は一般に割安で補償内容も職業にマッチしている利点があります。
自身の状況(フリーランスか法人経営か、保有資格の有無など)に応じて、上記の方法を選択してください。個人事業主でも法人向け保険に加入可能であることも覚えておきましょう(多くの損害保険は企業形態に関わらず契約できます)。
2. 必要書類の準備
保険の申し込み時には各社所定の申込書に加え、いくつかの証明書類が必要になる場合があります。一般的に要求されるのは本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)、そして場合によってトレーニング関連の資格証明書や開業届・商業登記簿謄本など事業の登録証明です。
普段あまり使わない書類の提出を求められることもあるため、紛失していると慌てることになります。事前にどんな書類が必要か確認し、手元に用意・保管しておきましょう。特に資格団体の保険に加入する際は資格番号や会員番号の記入が必要ですし、法人契約なら会社の登記情報が求められることもあります。
また、所得補償保険に加入する場合は現在の健康状態に関する告知書の提出が求められるのが一般的です。持病や過去の大きな傷病歴がある場合、保険料が割増になったり特定疾病が免責(対象外)になることもあります。
こうした加入審査(アンダーライティング)がある商品では、健康診断書や医師の診断書提出を指示されるケースもあります。
トレーナー特有の観点では、「過去に重大なスポーツ障害が無いか」「現在定期的に治療中の傷病は無いか」といった点がチェックされるでしょう。審査項目を事前に把握し、正直に情報提供することがスムーズな手続きのコツです。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
3. 保険契約時のチェックポイント
契約内容を決める段階では、次のポイントに注意しましょう。
- 補償範囲と対象確認: 加入する保険が自分の活動に伴うリスクを十分カバーしているかを確認します。例えば「他人への賠償」は入っていても「自身のケガ補償」が無ければ不安ですし、逆に傷害保険だけでは顧客への補償が漏れます。特に賠償責任保険の補償内容は要チェックで、指導中のあらゆる事故(対人・対物・施設被害など)に対応できるものを選びましょう。また対象となる職種や行為も確認し、パーソナルトレーナー業務がきちんと適用範囲に含まれているか見る必要があります。万一グレーな場合(例えば副業でマッサージ行為もする等)は事前に問い合わせておくと安心です。
- 保険金額と限度額設定: 賠償責任保険なら対人・対物それぞれどの程度の上限まで補償されるか、所得補償保険なら月いくら受け取れるか、傷害保険なら死亡・後遺障害時や入院日額はいくらか、といった補償額の設定を検討します。他社事例や想定リスクから妥当な金額を見極め、必要十分な補償額となるようにします。一般に対人賠償1億円は確保し、所得補償も現在の月収に見合う額で設定するのが目安です。
- 保険料の比較: 複数のプランがある場合、保険料負担とのバランスも考えます。同じような補償範囲ならできるだけ保険料が安いに越したことはありません。団体保険の割安さと、単独契約で自分に合った補償を自由に組み合わせる柔軟性のどちらを取るかもポイントです。補償内容と費用のバランスを総合的に判断し、最適なプランを選びましょう。
- 保険会社や商品プランの評判: あまり聞いたことのない保険だと不安な場合、業界での評判や口コミ情報も参考になります。実際に請求したときの対応スピードや、過去の支払い事例なども調べられれば理想です。ただし口コミは主観的な部分もあるため、最後は補償内容の充実度を重視すべきです。
- 契約期間と更新条件: 損害保険は通常1年更新が多いですが、契約期間や更新時の保険料改定条件なども確認します。団体保険の場合、資格を喪失(退会)すると保険継続できなくなることもありますので、更新漏れや退会に注意しましょう。事業拡大等で必要補償が変わった場合、更新時に見直すことも大切です。
- 免責事項と除外項目: 重要なのは「この保険では何が補償されないのか」を把握することです。例えば賠償保険でも、故意による損害や契約に背いた行為から生じた損害は補償対象外ですし、プロスポーツ選手に対する指導は除外、といった特約がある場合もあります。約款の免責事項を読み、自分の活動に関連しそうな除外条件がないかチェックしましょう。
4. 保険加入後の対応
契約が完了すると、保険会社から保険証券(加入内容を示す書面またはデータ)が発行されます。パーソナルトレーナーの場合、この保険加入証明を顧客やジム施設から求められることもあります(「賠償保険に入っている証明書を提出してください」と言われるケース)。常に提出できるよう、保険証券や加入証明書は手元に保管し、電子データ化できるものはスマホ等で確認できるようにしておくと良いでしょう。
また、万一事故が発生した際はすみやかに保険会社または代理店へ連絡し、事故状況を報告します。示談交渉を勝手に進めず、保険会社の指示に従うことも重要です(多くの賠償責任保険では保険会社が示談交渉サービスを行ってくれます)。事故対応の連絡先はすぐ確認できるよう控えておき、日頃から「もし〇〇な事故が起きたらまず連絡」とシミュレーションしておくと冷静に対処できます。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
まとめ
パーソナルトレーナーや小規模ジムのオーナーにとって、保険は事業と生活を守るライフラインです。顧客への安全配慮と同様に、自身の経営リスクにも目を向け、適切な補償を備えておきましょう。実例に見るように指導中の事故・トラブルは決して他人事ではなく、誰にでも起こり得るものです。
幸い、トレーナー業界には団体保険など手頃な商品も多数存在し、組み合わせ次第で事故の賠償から自身のケガ・収入保障、設備の補償までトータルにカバーできます。本記事で紹介した保険の種類や商品比較、事故事例を参考に、ぜひ一度ご自身の補償内容を見直してみてください。保険に加入していれば「万一のときどうしよう」という不安が軽減され、本業のトレーニング指導にも一層専念できるはずです。安全・安心な環境づくりのために、適切な保険への加入を検討しましょう。
パーソナルトレーナーの
検索&マッチングサイトへ登録しよう!

掲載費用&手数料が完全無料!
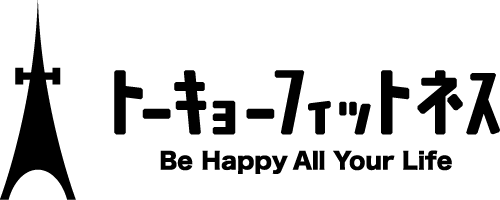
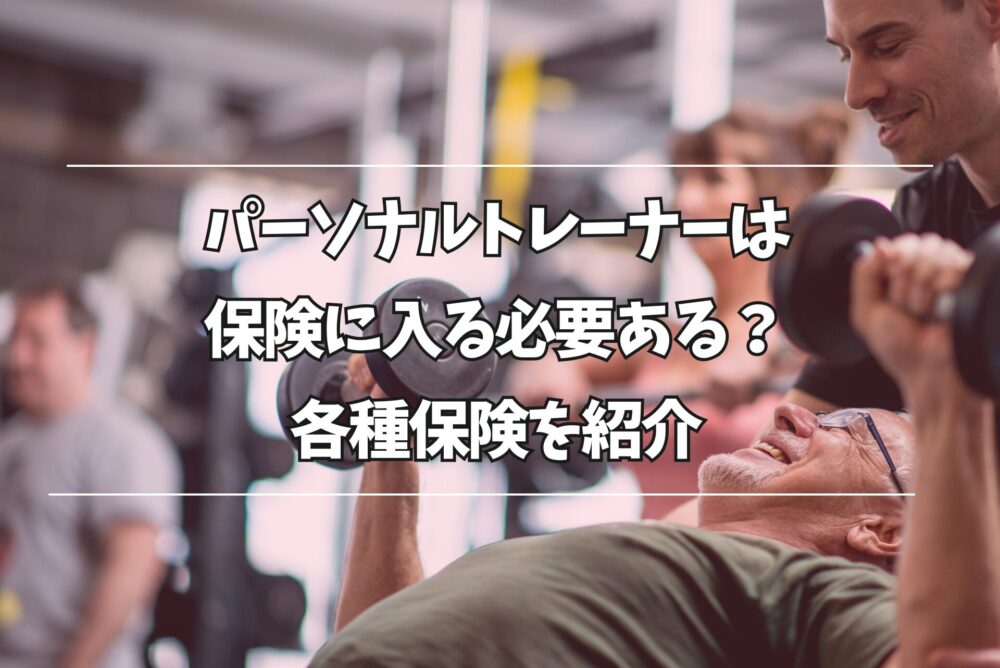
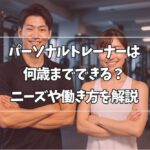

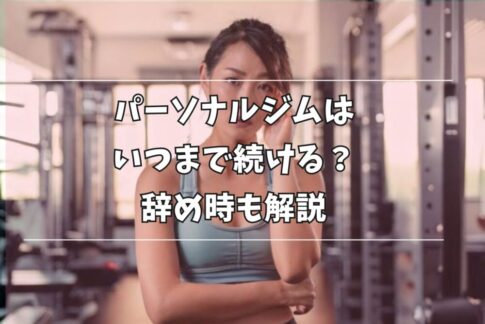


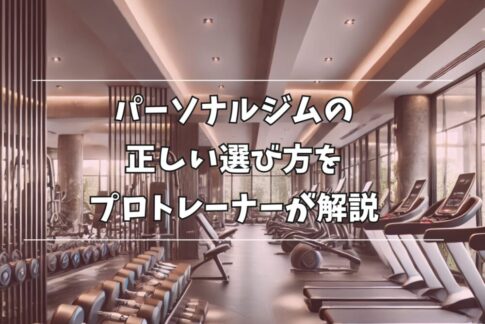
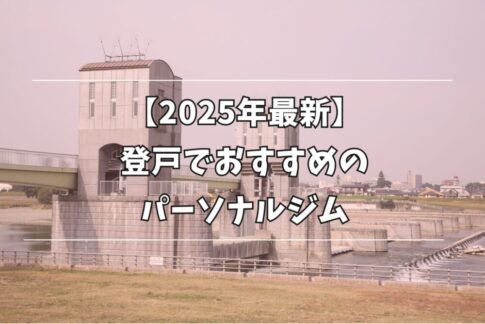





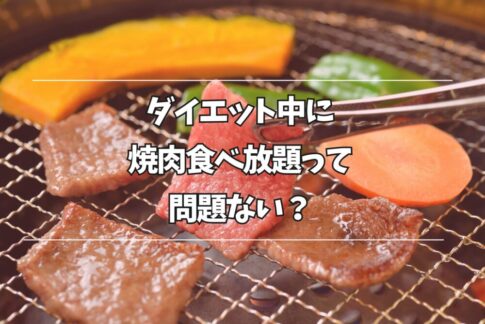
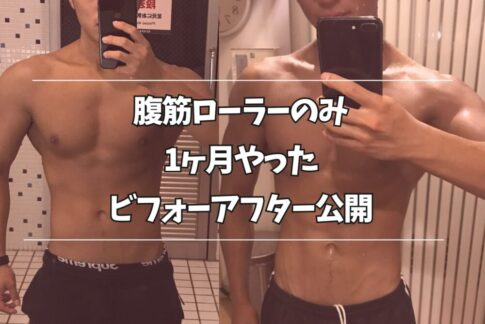

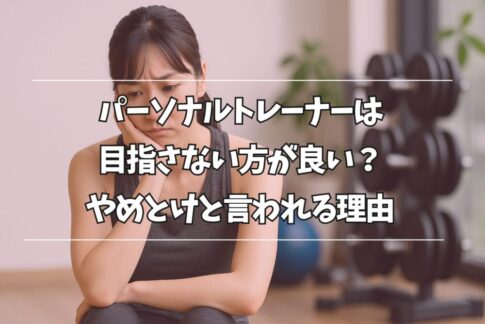


掲載費用&手数料が完全無料!