パーソナルトレーナーという職業に興味を持ちながら、インターネット上で「パーソナルトレーナー やめとけ」という言葉を目にして不安になっていませんか?
確かに、パーソナルトレーナーは一見華やかでやりがいのある仕事に思えますが、その裏には厳しい現実や苦労が存在するのも事実です。
この記事では、現役パーソナルトレーナーで生計を立てている私が、パーソナルトレーナーは「やめとけ」と言われる主な理由を丁寧に解説し、どんな人がこの仕事に向いていないのか、実際にネットで語られる本音や評判もご紹介します。
また、パーソナルトレーナーの将来性や可能性について考察し、それでもパーソナルトレーナーとして成功したい人のためのポイントも詳しくお伝えします。
パーソナルトレーナーの
検索&マッチングサイトへ登録しよう!
目次
パーソナルトレーナーは「やめとけ」と言われる理由

まず、なぜパーソナルトレーナーは「やめとけ(やめておけ)」と言われてしまうのか、その代表的な理由を見ていきましょう。
パーソナルトレーナーの仕事には表からは見えにくい厳しさがあり、憧れだけで飛び込んでしまうと理想とのギャップに苦しむことがあります。
以下に主な理由を挙げ、一つひとつ詳しく解説します。
理由①:収入が低く安定しにくい
パーソナルトレーナーは収入面の不安定さが指摘されます。
例えば、大手ジムに正社員として勤務すれば基本給がありますが、その額は決して高くなく、業界平均では年収300万〜400万円程度とも言われています。
多くの場合、基本給に加えて担当セッション数や物販(サプリメントやプロテインなど)の売上に応じたインセンティブが支払われます。
しかし、毎月安定してノルマを達成できる保証はなく、月によって収入が大きく変動することも珍しくありません。
フリーランスのパーソナルトレーナーや業務委託契約のトレーナーの場合はさらに収入が不安定です。
セッションを提供した分だけ報酬を得る形になるため、お客様がゼロの時は収入もゼロです。新規顧客を獲得できなかった月や、既存顧客が減ってしまったときは、そのまま収入減少に直結します。
実力次第で高収入も可能な世界ではありますが、裏を返せば「実力がなければ稼げない」厳しい歩合制の世界です。
こうした状況から、「生活を安定させるのが難しい」「家族を養うには厳しい」といった声が上がり、安易に飛び込むのはやめておけと言われる一因となっています。
特に貯金が少ない状態で独立開業してしまい、集客に苦戦して赤字になったという失敗談も聞かれます。収入を安定させるには工夫やビジネス戦略が必要ですが、何も知らないままでは低収入に陥りやすい職業と言えるでしょう。
理由②:長時間労働・体力的にきつい
パーソナルトレーナーの仕事は意外に長時間労働になりがちで、体力的にもハードです。一日の流れを想像すると、朝は早朝から出勤してモーニングトレーニングの顧客を指導し、日中は比較的時間が空いても勉強や事務作業、集客活動に充てます。
夕方以降は仕事帰りの顧客が集中するため、夜遅くまでセッションが続くこともしばしばです。結果として勤務時間が分散し、拘束時間が長くなる傾向があります。
また、肉体労働的な側面も見逃せません。トレーナー自身が常に身体を動かしてエクササイズのお手本を見せたり、器具の準備・片付けをしたりと、体力勝負の場面が多々あります。
一日に複数のセッションをこなすと、自分がトレーニングしたわけではなくてもかなりの疲労がたまります。特に立ち仕事で動き回るため、足腰への負担や体力消耗は軽視できません。
さらに休みが取りにくいという声もあります。顧客の都合に合わせて土日や祝日、平日夜間に働くことが多く、世間一般の休みのタイミングに仕事が集中しがちです。
お盆や年末年始もダイエット需要や顧客都合で忙しかったりと、プライベートの時間を確保しにくいケースもあります。「好きなことを仕事にしたのに、結局長時間労働で疲弊してしまった」という元トレーナーの後悔の声もネット上では見受けられます。こうした働き方の厳しさから、体力や時間面で「きつい」と感じて辞めてしまう人も多いようです。
理由③:競争が激しく集客が大変

近年のフィットネスブームもあり、パーソナルトレーナーの競争率は非常に高いです。国家資格が必須の職業ではないため、「筋トレが好き」「身体を動かす仕事がしたい」という人なら誰でも比較的参入しやすく、毎年多くの新人トレーナーが誕生しています。
その結果、都市部を中心にパーソナルジムやフィットネスクラブは乱立気味で、似たようなサービスが溢れている状態です。
競合が多いということは、お客様を獲得するハードルも高いということです。同じ地域や同じターゲット層を巡って多数のトレーナーが奪い合いをしているため、特に駆け出しの無名トレーナーにとって集客は大きな課題になります。
大手ジムに所属していれば集客面で多少サポートがあるものの、その分社内で他のトレーナーとの指名獲得競争があったり、インセンティブ獲得のプレッシャーがかかったりします。フリーランスであればなおさら、自分でSNS発信をしたりブログを書いたり、体験セッションを安価で提供したりと、営業・マーケティングにも労力を割かねばならず、トレーニング指導以外の時間も忙しいです。
質の良いサービスを提供することはもちろん大前提ですが、それだけでは埋もれてしまいかねないのが現状です。
差別化できる専門分野や、圧倒的な実績・肩書き(ボディメイク大会優勝経験や、スポーツの全国大会出場経験など)がないと、「どのトレーナーを選んでも同じ」と思われてしまう恐れもあります。こうした激しい競争環境に嫌気がさし、「こんなに頑張っているのにお客様が集まらない」と挫折してしまうトレーナーも多いようです。
理由④:お客様対応の難しさ・精神的負担
パーソナルトレーナーの仕事は人と深く関わるサービス業でもあります。マンツーマンで長期間お客様に寄り添うため、ただトレーニングの知識があれば良いわけではなく、高度なコミュニケーション能力や気配りが求められます。
このお客様対応の難しさも、パーソナルトレーナーを続ける上で精神的な負担になるポイントです。
例えば、トレーナーとお客様の相性は非常に重要です。どんなにトレーナー側が頑張って指導しても、人間同士ですから相性が合わないこともあります。
一度関係がぎくしゃくすると、お客様のモチベーションが下がり結果が出にくくなったり、トレーナー側もストレスを感じたりして悪循環に陥ることがあります。
場合によっては、お客様からクレームを受けたり、途中で担当変更や退会を言い出されたりすることもあり、精神的に堪える場面です。「お客様に寄り添いたいのに、どうしてもうまく信頼関係を築けない」という歯がゆさから落ち込んでしまうトレーナーもいるでしょう。
また、お客様それぞれの目標・体質・生活背景に合わせて最適なプログラムを組み、日々の体調やメンタルにも気を配りながら指導するのは簡単ではありません。
「痩せない」「筋肉がつかない」と焦るお客様に対して、励ましつつ正しい方向に導くコーチングスキルが必要ですし、時にはプライベートな悩み相談を受けることもあります。
常にお客様にエネルギーを注ぐ仕事であるため、自分自身が落ち込んでいたり体調が悪かったりしても笑顔で振る舞わなければならないプレッシャーもあります。
このように、パーソナルトレーナーは単にトレーニング指導するだけでなくメンタル面のサポート役も求められるため、対人ストレスを感じやすい人にとっては相当な負担になるでしょう。お客様本位で動かなければいけない場面が多く、サービス精神と忍耐力が試される職業です。
理由⑤:業界の闇・ブラックな側面も?

華やかに見えるフィットネス業界ですが、その裏には「業界の闇」とも言えるブラックな側面が存在すると言われています。パーソナルトレーナーに関連する口コミや暴露話の中でよく挙がるものをいくつかご紹介します。
まず、労働環境や待遇面のブラックさです。前述の通り長時間労働になりがちな上に、新人時代には低賃金・サービス残業が横行しているケースもあります。
例えば、小規模なパーソナルジムではスタッフの数が少ないため、一人のトレーナーが受付や清掃、雑務まで兼任し、実質的に拘束時間が非常に長いということがあります。
それでいて基本給は最低賃金ギリギリ、インセンティブもわずかしか出ないとなれば、いわゆる「やりがい搾取」的な働かせ方と言われても仕方がありません。中には見習い期間と称して無給同然で働かされるなど、ブラック企業じみた話も耳にします。
次に、ノルマや営業のプレッシャーです。大手パーソナルジムなどでは月会費や回数券の販売ノルマ、サプリメントなど物販の売上目標が課せられる場合があります。
数字を達成できないと上司から厳しく詰められたり、雇用を切られたりするケースもゼロではありません。本当はお客様のためにならないと感じる高額商品を売らなければならず、「トレーニング指導より営業ばかりさせられる」と不満を募らせるトレーナーもいます。お客様に対しても過度な勧誘をすることになれば、良心との葛藤で精神的に辛くなるでしょう。
さらに、業界全体の質の問題も闇の一つです。
前述したように参入障壁が低いため、必ずしも十分な知識・技能を持たないままトレーナーを名乗る人も存在します。その結果、誤った指導でお客様にケガをさせてしまったり、効果のないトレーニングで時間とお金を浪費させたりといったトラブルも起きています。こうした「やばいトレーナー」が一定数いることで、真面目に取り組んでいるトレーナーまで含めて業界の信用が損なわれるという悪循環があります。
最後に、キャリアの限界という闇も指摘されます。後述しますが、トレーナーとして現場で働き続けることには年齢的・肉体的な制約がつきまといます。業界内では「若いうちだけの仕事」「一生の仕事にするには厳しい」といった見方も根強く、将来の展望が描きにくい点を不安視する声が多いのです。
現に、ある元トレーナーの方は「同僚のトレーナーが2年以内に全員辞めていった」「結局成功して長く続けられるのは一握りしかいない」と自身のnoteで告白しています。離職率の高さも業界の闇と言えるでしょう。
ちなみに、パーソナルトレーナーが何歳まで働けるのかについては、別記事で詳しく解説したので、併せてご覧になってみてください。
以上のように、収入や労働条件、モラル面や将来性において、パーソナルトレーナー業界にはいくつかのブラックな側面が存在します。
もちろん全ての職場・トレーナーが当てはまるわけではありませんが、理想だけではなく現実の厳しさもしっかり認識しておくことが大切です。このような闇を知らずに飛び込むと、「こんなはずじゃなかった」と後悔する羽目になりかねないでしょう。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
パーソナルトレーナーに向いていない人の特徴
ここまで見てきた理由からも分かるように、パーソナルトレーナーという仕事には向き不向きがあります。では、具体的にどういう人がこの仕事に向いていないのでしょうか。
自分が当てはまっていないか、チェックしてみてください。
1. 安定志向が強すぎる人
毎月決まった給料をもらい、将来も計画通りに収入が伸びていくような安定を求める人には、パーソナルトレーナーの世界は不向きです。
収入の項目で述べた通り、収入は変動しやすく成果次第。さらに雇用形態によっては社会保険や福利厚生も手薄です。経済的な安定や安心感を最重視する人は、この不安定さに耐えられずストレスを感じてしまうでしょう。
2. 人の話を聞くのが苦手な人
パーソナルトレーナーは常にお客様本位で物事を考える必要があります。自己アピールよりも相手のニーズを優先できないと務まりません。
自分の意見やトレーニング理論を押し付けるばかりで、人の話に耳を傾けないタイプの人は、お客様との信頼関係を築けず失敗しやすいです。
また、自分が目立ちたい・チヤホヤされたいという動機だけで始めると、地道なサポート役に徹しなければならない現実とのギャップに苦しむでしょう。
3. コミュニケーションや接客が嫌いな人
人と接するのが得意でない人、内向的で会話が弾まない人も向いていない傾向があります。トレーナーの仕事はトレーニング指導だけでなく、常にお客様とコミュニケーションを取りながら進める接客業です。
黙々と筋トレだけ教えていれば良いわけではなく、雑談でリラックスさせたり、悩みに共感して励ましたりといった「話術」も要求されます。人見知りで初対面の人と打ち解けるのに時間がかかる人や、サービス精神より自分のペースを守りたい人には、1対1の接客は大きなストレスになるでしょう。
4. 自分自身の体型や健康管理がおろそかになりがちな人
パーソナルトレーナーはお客様のお手本となる存在です。自分の体型や健康状態に説得力がないと、お客様からの信頼を得にくくなります。
例えばトレーナー自身が明らかに不健康そうであったり肥満体型だったりすると、「この人に指導されても大丈夫か?」と思われてしまいます。自分の体調管理やトレーニングを継続する自己管理能力が低い人は、指導者としての信用を損ないやすいため、この仕事には向いていないでしょう。
5. 勉強嫌いで向上心がない人
パーソナルトレーナーは生涯にわたって勉強と自己研鑽が必要な職業です。トレーニング理論や栄養学の新知見は次々と出てきますし、お客様のニーズに応えるために幅広い知識(メンタルヘルス、リハビリ、スポーツ医学など)を学ぶ必要があります。
最初に資格を取ったからもう安心、という姿勢ではすぐに時代遅れになってしまいます。もし「勉強は苦手」「仕事以外の時間は趣味に使いたい」という人だと、継続学習の負担に耐えられず成長が止まってしまうかもしれません。向上心がなく現状維持でいたいタイプは、激しい競争の中で埋もれてしまい、この仕事で成功するのは難しいでしょう。
6. 忍耐力がなくすぐに結果を求めてしまう人
パーソナルトレーニングの成果も、トレーナーとしてのキャリアも、一朝一夕には得られません。お客様の身体が変わるには時間がかかりますし、トレーナー自身が一人前として認められたり十分な収入を得たりするにも年月が必要です。
にもかかわらず短期間で結果が出ないとすぐ投げ出してしまう人、思い通りにいかないとイライラしてしまう人は、この仕事には向きません。地道な努力を積み重ね、粘り強く続けていく覚悟が求められるため、コツコツ型でない人には厳しい世界です。
以上が主な「向いていない人」の特徴です。当てはまるものが多いからといって絶対に無理というわけではありませんが、そうした部分を克服する意識がないと、パーソナルトレーナーとしてやっていくのは難しいでしょう。
逆に言えば、自分がこの仕事に向いている人の特徴(対人サービスが好き、コミュニケーション能力が高い、体力がある、忍耐強い、成長意欲が高い等)に合致するかを冷静に見極めることが大切です。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
私の体験談やネットで見かける「やめとけ」の評判・口コミ
実際にパーソナルトレーナーを経験した人たちの生の声も、ネット上には数多く投稿されています。
「やめとけ」と感じた具体的なエピソードや、逆に挑戦したけど挫折した人の後悔など、リアルな評判を見てみましょう。
私の体験談

私は2022年からフリーランスのパーソナルトレーナーとして独立をし、現在も生計を立てています。
正直最初の2年は以下の理由でとても辛い思いをしました。
- 急に1人で仕事するため、仲間がいなくなった孤独感
- 新規の集客ができないときに既存顧客が退会した時の焦り
- 将来への不安
これらは、あらかじめ現状を把握し、パーソナルトレーナーとして活動する上でどういった心構えや準備が必要かをもっと考えてから行動すれば解決できていたと今でも思います。
あくまでも、フリーランスとして活動した体験談ですが、大手のパーソナルジムやフィットネスジムで働いていても同様です。
周りのトレーナーが人気があるのに自分だけ集客できない時の不安。一日8本以上のレッスンをやっても対価が見合わないと感じてしまうなど、なんとなく「パーソナルトレーナーは稼げる」と思うだけでは正直厳しい世界と言えるでしょう。
noteに見る失敗談・後悔の声

また、ブログサービス「note」には、現役・元パーソナルトレーナーによる体験談がいくつも投稿されています。その中には、「トレーナーを職にするのはやめとけ?!」「業界の闇を全てお伝えします」といったタイトルで、業界の現実を赤裸々に語る記事もあります。
ある現役トレーナーのnoteでは、パーソナルトレーナー業界の理想と現実のギャップについて綴られていました。その筆者自身、トレーナー養成スクールの講師を務める方で、業界に飛び込んだ新人たちが直面する問題を多数目の当たりにしてきたそうです。例えば、
- 「対価に見合わない低賃金・無給労働」に苦しんだ話
- 「売上ノルマ達成のためにお客様に不必要なサービスまで売らざるを得なかった」というジレンマ
- 「相性が合わないお客様にも我慢してサービス提供し続け精神的に疲弊した」経験
- 「キャリアアップにつながらない雑務やサービス残業ばかりで将来に不安を感じた」という不満
- 「独立したい気持ちはあるが行動に移せず悩むうちに年齢だけ重ねてしまった」という停滞感
- 「名乗れば誰でもトレーナーになれる業界なので、レベルの低いトレーナーが多く現場がカオスだった」という嘆き
などが具体例として挙げられていました。
その記事によれば、筆者が働いていたあるジムではトレーナー5人全員が2年以内に退職し、他のジムでも離職率の高さは珍しくないとのことです。
さらに印象的なのは、「フリーで自立して食べていける成功者はせいぜい1割程度だろう」という厳しい予測が述べられていた点です。つまり、大半のトレーナーは思い描いた理想とは違う現実にぶつかり、どこかで道半ばに諦めてしまっているというのです。
別のnoteでは、新卒でパーソナルトレーナー就職を選んだ筆者が「やめとくべきだった」と振り返るエピソードもありました。
その方は筋トレが好きという単純な理由で専門学校卒業後すぐパーソナルジムに就職したものの、過酷な労働環境と将来性のなさに絶望して退職しています。
「トレーナーはいつでも誰でもなれる仕事だから、青春の貴重な時期を使うのはもったいない。もっと若いうちは伸びしろの大きい分野にチャレンジすべきだった」という趣旨のことを述べており、軽い気持ちで飛び込んだことを悔やんでいました。
これらのnoteに共通するのは、「好き」だけでは乗り越えられない壁が多いという現実です。
好きなトレーニングを仕事にできる喜び以上に、ビジネス面やメンタル面の厳しさに直面して苦労したという声が目立ちます。「こんなはずじゃなかった」「事前にもっと情報が欲しかった」と後悔する人も多く、これが「やめとけ」と言われる背景にあることがよく分かります。
2chなど掲示板で語られる本音
匿名掲示板の2ch(現5ch)や知恵袋のようなQ&Aサイトでも、パーソナルトレーナーに関する本音トークが見られます。こちらではより率直で辛辣な意見が飛び交うこともあります。
例えば、ある掲示板では「パーソナルトレーナーって底辺の仕事?」といったスレッドが立ち、議論が行われていました。
その中では「トレーナーは結局ジムの雑用係」「好きな筋トレも仕事になれば苦痛」「稼げなくて結婚もできない」といった厳しいコメントが並んでおり、夢のない現実が語られています。また「筋肉があるウェイターみたいなもの」「体育会系ブラック業界だから長く続かないよ」など、きつい労働の割に報われないイメージを持つ人もいるようです。
Yahoo!知恵袋のある質問では、29歳男性が未経験からトレーナーを目指すべきか相談していました。それに対する回答で印象的だったのは、「年齢の問題じゃなく、収入が無くても生きていけるくらい覚悟と蓄えがないならやめといた方がいい。トレーナー専業では先が無い」という趣旨のアドバイスです。
さらに、「トレーナー養成スクールは声優やアニメーターの専門学校と同じで、通ったところで食べていける保証はない」「資格を持っていても集客力には直結しない」とも述べられていました。結局、「よほど突出した経歴がある人か、SNSで影響力を持って自力で集客できる人でないと成功は難しい」という手厳しい現実を突きつけています。
このように、匿名の場ではよりシビアに「パーソナルトレーナーは割に合わない」「よほどの覚悟が必要」という本音が語られています。
もちろん、中には「自分は充実している」「努力次第で稼げる」というポジティブな声もありますが、全体としては警鐘を鳴らす意見が目立つ印象です。「やめとけ」という言葉の裏には、そうした先輩たちの苦労や挫折からくるリアルな叫びがあることを、心に留めておいた方がいいでしょう。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
パーソナルトレーナーの将来性と可能性

ここまでネガティブな面を中心に述べてきましたが、ではパーソナルトレーナーという職業に将来性はあるのか、明るい展望はないのでしょうか。
結論から言えば、業界全体としての需要は今後も拡大が見込まれる一方、個々のトレーナーが将来にわたって活躍できるかは工夫次第といえます。
パーソナルトレーニングのニーズ
まず需要面では、近年の健康志向ブームによりパーソナルトレーニングを利用する人は確実に増えています。ダイエットや筋力アップはもちろん、肩こり腰痛の改善や生活習慣病予防、シニア層の健康維持など目的は多様化しており、パーソナルトレーナーが活躍できるフィールドは拡がっています。
特に高齢化社会の日本では、シニア向けの運動指導やリハビリ的トレーニングのニーズが高まっており、今後もトレーナーの必要性自体は十分にあるでしょう。海外ではパーソナルトレーナーが医療・福祉分野と連携して活躍するケースも増えており、日本でも健康寿命を延ばすためのパーソナルトレーニングが注目されています。
オンラインやAIの活用など新しい働き方
また、ここ数年でオンラインパーソナルトレーニングやフィットネス系アプリなど、新たなサービス形態も出てきました。
遠方の顧客をビデオ通話で指導したり、AIやデータを活用して効率化を図ったりと、テクノロジーとの融合でビジネスチャンスは広がっています。
トレーナー自身がSNSやYouTubeで情報発信し、インフルエンサー的に活躍して収入を得るモデルも生まれています。こうした時代の流れに乗り、新しい働き方を取り入れられるトレーナーにとっては、将来性は決して暗くありません。
トレーナー人口の増加が激しい
一方で、競争が激しい点は将来も変わらないどころか、ますます熾烈になる可能性があります。需要拡大とともに参入者も増えていますから、「トレーナー人口の増加 = 一人当たりの取り分が減る」構図も考えられます。
つまり、将来性があるかどうかは、「単に市場が伸びるか」ではなく「自分がその中で選ばれる存在になれるか」にかかっているのです。
どんなに市場規模が拡大しても、競合に埋もれてしまえば収入やキャリアは伸び悩むでしょう。
キャリアアップの可能性
個人のキャリアという観点では、前章までに触れた年齢や体力の問題も無視できません。パーソナルトレーナーは若いうちだけ…と決めつける必要はありませんが、事実として若くエネルギッシュなトレーナーが好まれたり、自分自身が加齢で体力的にハードな現場が辛くなる可能性はあります。
将来的に現場を離れてマネジメント側に回る道や、独立してジム経営者になる道もありますが、そうしたポジションは数が限られ、全員が辿り着けるわけではありません。業界内でも「店長止まり」「生涯現場はキツい」という声があり、キャリアアップの機会が少ない点を不安視する人は多いです。
もっとも、だからといって悲観する必要はなく、キャリアの可能性を自分で切り拓いていく余地は十分にあります。
例えば、トレーナーの経験を積んだ後に理学療法士や柔道整復師の国家資格を取ってリハビリ分野に進出する人や、管理栄養士の資格を取って食事指導もできるトレーナーになる人もいます。また、大手ジムの本部スタッフとして店舗運営や新人育成に関わる道、専門学校やスクールの講師となって次世代トレーナーを育てる道、さらには独立して自分のブランドを確立しフランチャイズ展開するような野心的な道も考えられます。
要するに、パーソナルトレーナーの将来性は「業界として需要があるか」と「自分自身がキャリアを広げられるか」の両面で考える必要があるでしょう。
需要面では明るい兆しがありますが、個人として成功し続けるには環境の変化に適応し、学び続け、差別化を図る努力が不可欠です。
次の章では、その「パーソナルトレーナーとして成功するには」というポイントについて具体的に見ていきます。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
パーソナルトレーナーとして成功するには
ここまでの内容を踏まえると、パーソナルトレーナーとして長く活躍し成功していくためには、相応の工夫と努力が必要なのは明らかです。「やめとけ」と言われる厳しい側面を乗り越え、自分なりのやりがいと安定を得るにはどうすれば良いのでしょうか。最後に、パーソナルトレーナーとして成功するためのポイントをいくつかの観点から解説します。
成功のカギ①:安定収入を得るための工夫と戦略

成功のためには、まず収入面の安定化を図る戦略が欠かせません。パーソナルトレーナーとして食べていけるようになるまでに時間がかかることも多いため、計画性を持ってキャリアを積みましょう。
複数の収入源を持つ
トレーナー一本に固執せず、関連する仕事を掛け持ちすることでリスク分散する方法があります。
たとえば、パーソナルトレーニングの傍らフィットネスクラブのインストラクターやジムスタッフのアルバイトをしたり、グループレッスンを担当したりすることで固定収入を補うことができます。
また、トレーニングに関するブログや動画配信で広告収入を得たり、書籍や教材を制作して販売したりする人もいます。
最近はオンラインで完結する指導サービスもあり、対面セッション以外の商品を持つことで、時間や場所に縛られない収入源を作ることも可能です。こうしたマルチな働き方によって、特定のクライアントや季節需要に収入が左右されにくくなります。
集客とリピーター獲得の戦略
安定収入の鍵は、継続的にお客様に来てもらうことです。そのためには新規集客だけでなく、既存のお客様に長く続けてもらう工夫が重要です。
例えば、初回お試しを低価格で提供してハードルを下げたり、ビフォーアフターの成功事例をSNSで発信して興味を惹いたりするのは新規集客に有効でしょう。
リピーター対策としては、定期的に目標設定を見直してマンネリ化を防いだり、セッション外でもLINEやメールでフォローアップしてモチベーション維持をサポートしたりする方法があります。
また、回数券や月額プランなど長期契約の商品を用意し、お客様が途中でやめにくい仕組みを作るのも一つです。満足度の高いサービスを提供すれば口コミ紹介も期待できますから、目の前の顧客一人ひとりを大切にし信頼を積み重ねることが、結果的に安定収入につながります。
ビジネススキルを磨く
トレーナーであっても経営者視点や営業スキルは必要です。特に独立している場合、自分自身が商品の営業マンでもあります。
マーケティングの基礎知識(ターゲット設定、ブランディング、SNS活用など)や、お金の管理(確定申告、経費計上、価格設定の戦略)といったビジネススキルを身につけておくと、収入のアップダウンをコントロールしやすくなります。
筋トレの勉強ばかりでなく、経営や営業の勉強にも時間を割いてみてください。副業からスタートする場合も、最初は現職の収入で生活費を賄いながら、トレーナー収入はすべて貯蓄や投資に回すくらいの慎重さで臨むと安心です。そうして資金的な土台を作りつつ顧客を増やしていけば、いざ一本に絞る際のリスクも軽減されるでしょう。
成功のカギ②:専門知識の習得と継続学習で差別化

成功するトレーナーになるには、「知識は力」です。体づくりに関する専門知識を深め、他のトレーナーとの差別化を図りましょう。
分野を絞って専門性を高める
まず、自分が特に情熱を注げる分野や得意とする領域を見極め、それを徹底的に掘り下げて専門家レベルを目指すのがおすすめです。
例えば、「ダイエット・ボディメイク専門」「産後ママ向けフィットネス」「シニア向け健康づくり」「アスリートの競技力向上」「リハビリ・コンディショニング」など、何でも屋になるより「○○ならこの人」と言われる強みを持つ方が選ばれやすくなります。
その分野に関する勉強会やセミナーに積極的に参加し、関連資格があれば取得すると良いでしょう。専門性が高まればお客様からの信頼度も上がりますし、多少競合が増えても埋もれにくくなります。
資格取得や認定を活用する
パーソナルトレーナー関連の資格には、NSCA-CPTやNESTA、JATI、公的資格の健康運動指導士など様々あります。
資格自体があれば即食べていけるわけではありませんが、体系的に知識を学ぶ指針にはなりますし、顧客や雇用先に対する一定のアピール材料にもなります。
また、栄養士・管理栄養士、理学療法士、鍼灸師など他分野の資格を組み合わせれば提供できるサービスの幅も広がります。
自分のキャリアプランに沿って、「この資格を持っているトレーナーは少ない」「この組み合わせは希少だ」というものを狙ってみるのも手です。ただし資格は取得して終わりでなく、取った後に知識をどう生かすかが大切なので、現場でアウトプットしながら定着させていきましょう。
最新情報をキャッチアップし続ける
健康・フィットネスの分野は日進月歩で、新しいトレーニング理論やエビデンス、ツールが次々登場します。成功するトレーナーは常にアンテナを張り、アップデートを怠りません。
研究論文や専門誌を読んだり、著名トレーナーの発信をチェックしたりして、「昨日より今日、去年より今年」の自分の指導力を高める意識を持ちましょう。
もちろん流行に振り回されすぎる必要はありませんが、知識が古いままだと顧客にも見透かされてしまいます。
「この前テレビで見た○○法ってどうなんですか?」など質問されることもあるので、引き出しは多い方が安心です。継続学習は大変ですが、それ自体を楽しむくらいの気持ちで取り組むと、いずれそれが他人に真似できない財産となって返ってきます。
成功のカギ③:コミュニケーション力と信頼関係の構築

成功するパーソナルトレーナーに共通しているのは、技術以上に人間的な魅力と信頼感があることです。お客様との強い信頼関係を築くためのコミュニケーション術を磨きましょう。
傾聴と共感を心がける
お客様は様々な不安や悩みを抱えてトレーニングに来ています。その声に真摯に耳を傾け、「あなたの気持ちを理解していますよ」という姿勢を示すことが大切です。
結果が出せず悩んでいる人には寄り添い、些細な変化でも一緒に喜ぶ、そんな共感力が求められます。トレーナーが上から目線で「頑張りが足りない」などと責めてしまえば関係は壊れてしまいます。
逆に、親身になって話を聞き励ましてくれるトレーナーには、人は心を開きやすくなり、多少厳しいトレーニングもついてきてくれるものです。まずは相手の話を遮らず最後まで聞く、一度受け止めてから提案する、といった傾聴の基本を実践しましょう。
分かりやすく伝える力
トレーニング指導では専門用語や複雑な理論を扱いますが、お客様にとって理解できなければ意味がありません。難しい話を噛み砕いて例えを使って説明する力も重要です。
たとえば「ハムストリングスを鍛えましょう」と言うより「太ももの裏の筋肉を鍛えてヒップアップしましょう」と言った方が伝わりますし、「姿勢が悪いですよ」より「もう少し胸を張ってみましょう、その方がかっこいいですよ」とポジティブに伝える方が受け入れられやすいでしょう。
専門知識があるからこそ、それを相手に合わせて伝えるコミュニケーション能力を磨いてください。笑顔やユーモアも大切なスキルです。苦しいトレーニング中に冗談を交えて笑わせるくらいの余裕があると、お客様との距離も縮まります。
信頼は小さな積み重ね
信頼関係は一朝一夕には築けません。時間を守る、約束を守る、常に安全に配慮する、嘘をつかないといった基本的なことを徹底し、プロフェッショナルとしての信用を積み上げることが重要です。
例えば「このトレーナーに任せれば安心」「何かあっても真剣に向き合ってくれる」という安心感があると、お客様はずっとついてきてくれます。逆に、一度でもいい加減な対応をしたり不誠実な言動があったりすると、簡単に信頼は崩れてしまいます。
また、常にトレーナー自身が健康的でポジティブなライフスタイルを体現することも信頼に繋がります。自分が疲れて不機嫌だったり体調管理ができていなかったりすると、お客様に対して説得力がなくなってしまいます。自ら模範となり、言行一致の姿勢を見せることが長期的な信頼構築には欠かせません。
成功のカギ④:キャリアビジョンを明確に描く

最後に大切なのは、自分なりのキャリアビジョンを持つことです。目先のセッションをこなすだけではなく、将来どんなトレーナーになりたいのか、どんなライフプランを実現したいのかを明確に描いておきましょう。
目標設定と逆算
例えば、「5年後に自分のパーソナルジムを開業する」「有名アスリート専属のトレーナーになる」「オンラインで○○人の会員を抱えるサービスを作る」など、大きな目標を設定してみてください。
その目標から逆算して、1年後・3年後には何を達成しておくべきか考えます。必要な資格取得や経験、人脈づくりの計画を立て、段階的にクリアしていくイメージです。
明確な目標があれば、日々の仕事にも軸ができ、モチベーション維持にも役立ちます。逆に目標がないと流されてしまい、「気づいたら年だけ取ってキャリアが停滞していた…」ということにもなりかねません。
柔軟なキャリアパス
キャリアビジョンは一つではなく、いくつかのシナリオを用意しておくのも良いでしょう。たとえ最初の計画が思い通り進まなくても、代替案があれば落胆せずに次のチャレンジに移れます。
「もし独立が難しければ業界内でマネージャー職を目指そう」「パーソナルトレーナー経験を活かしてフィットネス商品の開発やセールスに転身するのもアリ」など、視野を広く持つと選択肢が増えます。
パーソナルトレーナーという仕事は決して無駄にはなりません。培った知識とコミュニケーションスキルは、健康産業やスポーツビジネス、教育分野など様々な所で活かせます。自分のキャリアを自分で限定しすぎず、変化に応じて路線変更も辞さない柔軟さが長い目で見ると強みになります。
ライフプランとの調和
キャリアばかりに目を向けず、プライベートも含めたライフプラン全体で考えることも重要です。結婚や家族の予定、マイホーム取得や老後の設計など、人生全体の中でトレーナーという仕事をどう位置付けるかを考えてみてください。
例えば「子育て期は安定収入の職に就き、子供が大きくなったらトレーナーで独立再挑戦する」など、人それぞれ事情があります。
トレーナーという働き方はフレキシブルでもありますから、自分や家族の状況に合わせてキャリアの比重を変えることも可能です。
長期的な視野で見れば、一時的にトレーナー業を離れて別の仕事やスキルを身につけ、それから復帰するという選択肢もありえます。大切なのは、自分の人生にとって何が幸せかを見失わないこと。その上でパーソナルトレーナーという仕事をどう活用していくかを考えましょう。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
まとめ
パーソナルトレーナーは一見華やかで「好きなことを仕事にできる」魅力的な職業です。しかし、その裏側には収入の不安定さ、長時間労働、激しい競争、お客様対応の難しさ、業界特有の闇など、決して楽ではない現実が横たわっています。そのため、ネット上でも「やめとけ」「割に合わない」といった否定的な意見が出てくるわけです。実際に多くの人が理想とのギャップに悩み、早期離職してしまうケースも少なくありません。
ただ、「やめとけ」という言葉だけで自分の夢を諦めてしまうのは少し早計かもしれません。大切なのは、現実を正しく知った上で、それでもなお挑戦したいか、自分にその覚悟と適性があるかを見極めることです。本記事で挙げたような厳しい側面に対して、「自分なら工夫して乗り越えられそうだ」「努力してでもトレーナーになりたい強い動機がある」と思えるなら、決して道は閉ざされていません。
パーソナルトレーナー業界は需要も伸びており、工夫次第で活躍の場を広げていける可能性があります。成功する人はごく一部…と言われがちですが、その一部に入るためのヒントも数多く存在します。安定収入の工夫、専門性の追求、コミュニケーション力の向上、明確なキャリアビジョンなど、できる準備を着実に進めていけば、「やめとけ」と言われる職業を「あえて選んでよかった」と胸を張れる日が来るかもしれません。
最後に、この記事を読んで「やっぱり自分には難しそうだ」と感じたなら、無理に進む必要はありません。他の道で健康やトレーニングの知識を活かす方法もありますし、趣味として筋トレを楽しみ続ける選択も素晴らしいことです。
一方、「厳しいこともあるけれど挑戦してみたい!」と思えた方は、ぜひ慎重に準備をしながら一歩踏み出してみてください。現場でしか得られないやりがいや感動もきっとあります。不安と向き合いつつも自分の情熱を大切に、悔いのないキャリア選択をしていけるよう願っています。
トレーナー向けマッチングサイトへの
掲載費用&手数料が完全無料!
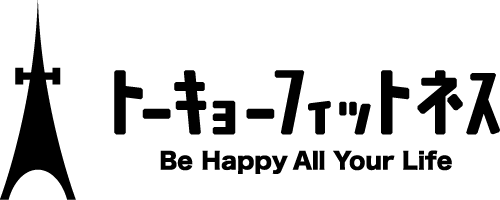
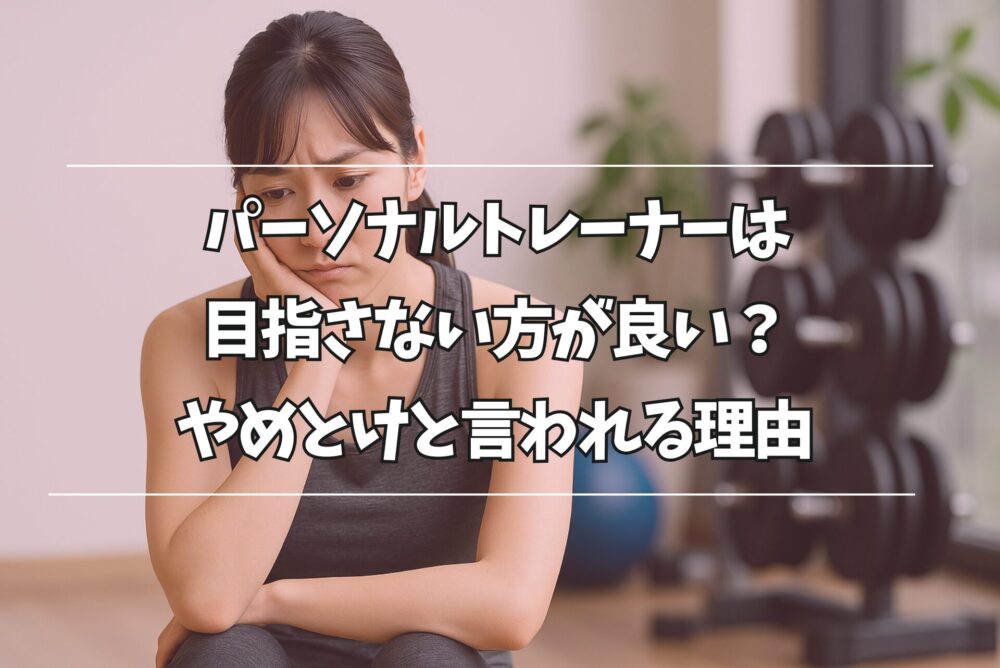
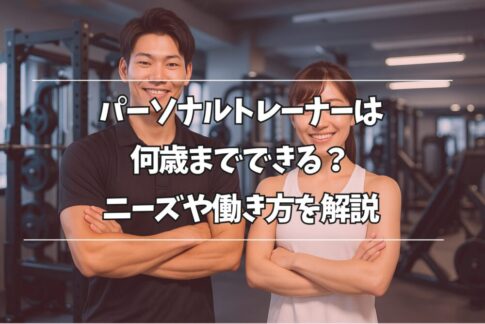

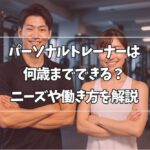










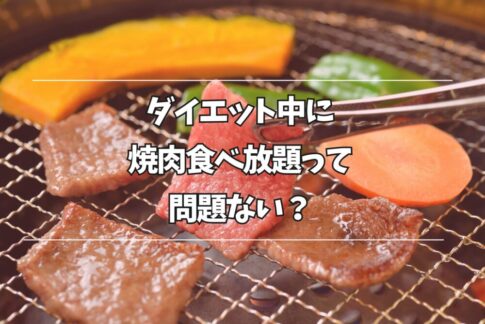
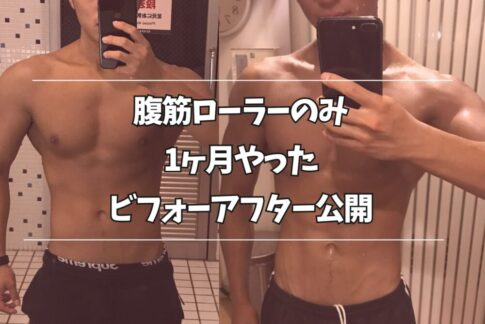

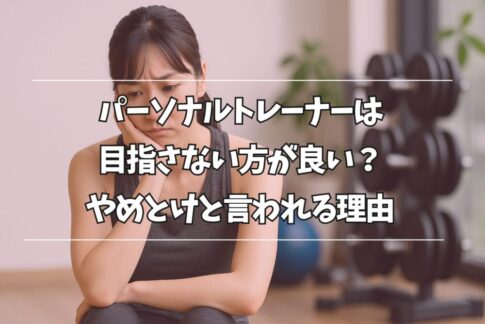


掲載費用&手数料が完全無料!